突然ですが質問です!
筋トレを始めたものの途中で
やめてしまった経験はありませんか?
筋トレに限らず、何かを始めても
続かないという人は多いのではないでしょうか?
これは決してあなたの意志が弱いのではなく、
続けられない明確な理由があるのです。
その理由を科学的根拠をもとに
「意志に頼らない方法」として、
一年半以上自宅トレーニングを
続けている著者が解説していきます。
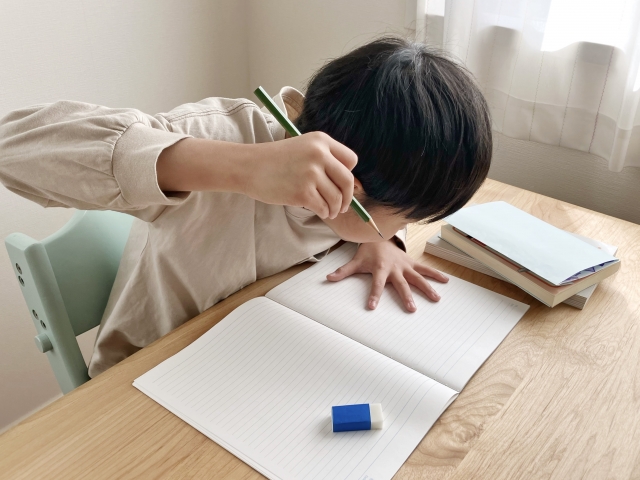
実は私もこの事実を知る前は、
何を始めても続かず、
自信をもって人の目を見て
話すことができなかったり、
自信のなさから無理に
自分を大きく見せようとしたり、
何事もネガティブにとらえて
落ち込みやすかったり、
恥ずかしいという理由で
行動をやめてしまったり,
まだ若いのに、肩こり、腰痛に
悩まされていたりと
そんな日々を過ごしていました。
しかし筋トレを始めてからは、
自信をもって人の目を見て話せるようになり、
人前でも堂々とふるまえるようになり、
物事をポジティブにとらえて気分も上がり、
行動が続けられるようになり、
スタイルを褒められてさらに自信がつき、
肩こりや腰痛がなくなって
毎日すっきり過ごせるようになったのです。
筋トレを始めてから、私の人生は大きく好転しました!
この記事では、そんな筋トレを
「続けられる方法」を具体的に紹介していきます。
あなたもこの方法を知ることで、
自分の人生をより良いものに変えていきましょう!

なぜ多くの人が続けられないのか!?
なぜ多くの人は続けることができないのでしょうか?
その理由を「意志力が弱いから」と
考える人も多いかもしれませんが、
実はそうではなく、
習慣化の方法を知らないことが
根本的な原因なのです。
「方法を知っただけで本当に続けられるの?」
と思うかもしれませんが、安心してください!
習慣化の仕組みを理解すれば、
今までよりも断然続けやすくなるでしょう!
結論から言えば、
大切なのは「毎日続けること」です。
「そんなことはわかってる!」
と思う方もいるでしょう。
ではなぜ“毎日”続けることが重要なのか?
ここを理解していない人は、
これからも続けることが難しいかもしれません。
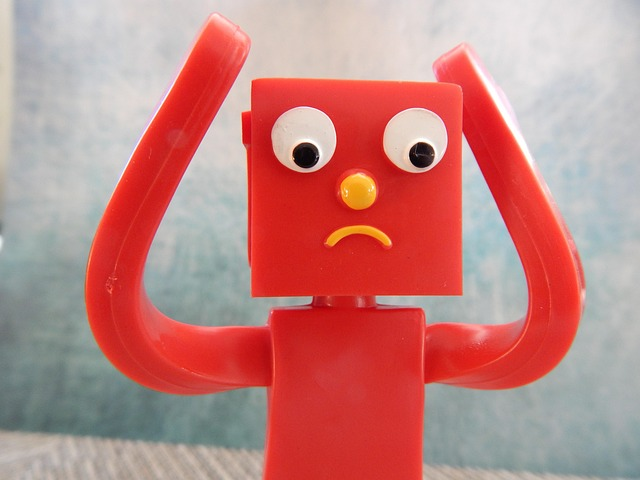
「理由なんていいから方法だけ教えて!」
という方もいるかと思いますが、
人それぞれ生活スタイルが違い、
自身に合ったやり方も異なります。
だからこそ根本的な理由を知り、
自分に合った形に応用することが必要なのです。
これがわかれば、ただ「続ける」だけでなく
「楽して続ける」方法も見えてきます。
そこで次に、続けられるための方法を
3つのポイントに絞って解説していきます。
習慣化とドーパミンの関係
習慣化には、脳内のドーパミンという快楽物質が大きく関わっています。
ドーパミンは「報酬の予測」と「実際の結果」の差に
反応する性質を持っています。
要約すると以下のようになります。
- 期待より良い結果 → ドーパミン放出↑(行動が強化され、学習が進む)
- 期待通りの結果 → ドーパミン変化ナシ(学習は起きない)
- 期待より悪い結果 → ドーパミン活動低下(行動は弱まる)
つまり、期待以上の結果を得られると習慣化につながりやすいのです。
多くの人がつまずく理由
ここで問題なのが、多くの人が筋トレに対して
「思っている以上にすぐ効果が出る」と勘違いしている点です。
- 「筋トレを始めたら、すぐに筋肉がつくはず」
- 「続けていたら、すぐに理想の体になれる」
こうした過剰な期待を持ってしまうと、
思うように結果が出ないときに
「期待より悪い結果」と感じてしまい、
ドーパミンが下がり、習慣が続かなくなるのです。
また、「筋トレするとムキムキになりすぎるのが嫌」
と心配する人もいますが、
実際にはそんなに簡単に筋肉は大きくなりません。
もし簡単にムキムキになれるなら、
世の中のみんながすでにマッチョになっているはずです。
要するに、
習慣化できない理由のひとつは
「報酬の予測がズレている」ことなのです。
習慣化のための正しい視点
そこで大切なのは、
筋肉が見た目に変化するまでに
どのくらい時間がかかるかを正しく理解すること
もちろん効果が出るスピードは人によって違いますが、
一般的に筋トレの成果が目に見えて分かるようになるには
数か月単位の継続が必要です。
この「時間の目安」を知っているかどうかで、
習慣を続けられるかが大きく変わってきます。
習慣化のコツ
習慣化のコツは、
結果にばかり期待しないこと
「体が変わったかどうか」よりも、
「今日も行動できた自分」を見つめて
小さな喜びを感じること。
- たとえば「腕立てを1回やった」だけでも
「続けられた自分」を褒める - 「よし、今日もできた」とにやにやしてみる
このように行動そのものを報酬に変えることで、
ドーパミンが分泌されやすくなり、
習慣化がぐっと楽になります。
要約
- ドーパミンは「期待と結果の差」に反応する
- 習慣化できないのは「期待が高すぎるから」起こることが多い
- 成果は数か月単位で現れると理解することが大事
- 結果よりも「続けている自分」を褒めることでドーパミンを活用できる

習慣化と脳エネルギーの関係
習慣化が難しい理由のひとつに、
前頭前野の働きがあります。
前頭前野は「意志力の中枢」であり、
行動を始めるためのアクセルや
「やめる」ためのブレーキの役割を担っています。
しかし、前頭前野は脳の中でも
特にエネルギーを多く消費する部位です。
一日の脳エネルギーの総量は人によって決まっており、
そのため新しい行動を起こそうとすると、
一気に脳のエネルギーを使い、すぐに疲れてしまうのです。
疲れていると続かない理由
例えば、仕事や学校が終わった後に
「筋トレをしよう!」と思っても続かないのは、
すでに脳のエネルギーが減っているから。
この状態では「今日は疲れているから明日でいいや」
といった言い訳が出やすくなります。
これは怠けではなく、脳の仕組みによる自然な反応です。
習慣化するとどうなる?
ところが、一度行動が習慣化されると状況は変わります。
習慣化された行動は、前頭前野をあまり使わず、
自動的にできるようになるからです。
例えば、歯磨きや自転車、車の運転を
毎回「よし、やるぞ!」と
気合を入れてやってはいませんよね。
疲れていても自然にできるのは、
すでに習慣として脳に組み込まれているからです!
脳エネルギーの限界と回復方法
脳のエネルギーには上限があります。
これを超えると意思決定のミスが増えたり、
やる気が出なかったり、集中力が切れたりします。
そのエネルギーを回復させる方法は主に3つです。
- 睡眠や仮眠をとること
- 食事をして栄養を補給すること
- 軽い運動で血流を促すこと
これらはよく知られていますが、
もうひとつ重要なのが スマホの使い方 です。
スマホは意外なエネルギー泥棒
「スマホを触っているときは休めている」
と思うかもしれませんが、実は逆。
情報を処理し続けているため、
脳は休むどころかエネルギーを消費し続けています。
つまり、無意識にスマホを長時間使っていると、
それだけで脳エネルギーが削られ、
肝心な行動を起こす力が残らなくなってしまうのです。
要約
- 新しい行動=脳エネルギーを大量に消費する
- 習慣化すればエネルギー消費は減り、自動的に行動できる
- 習慣化のコツは「小さく始めて前頭前野への負担を減らすこと」
- 脳エネルギーは睡眠・食事・運動で回復する
- ただしスマホは「休憩」にならず、エネルギーをむしろ奪う

習慣化にかかる期間と脳の仕組み
「習慣化にはどのくらいの期間が必要なのか?」
この目安を知っているだけで、
行動目標や計画を立てやすくなります。
ロンドン大学の研究によると、
習慣化には平均66日かかるとされています。
ただしこれはあくまで平均で、
実際には18日~254日と大きな個人差があります。
- 行動が小さいほど → 習慣化は早い
- 行動が大きいほど → 習慣化には時間がかかる
ここを理解しておくことがとても重要です。
習慣化のポイント
習慣化において大切なのは次の2点です。
- 小さく始めること
→「毎日腕立て10回」より
「とりあえずマットに寝転ぶ」くらいの小ささでOK - 休んでもリセットされないことを知ること
→ 習慣化は「一度休んだからゼロに戻る」ものではありません。
「今日はできなかった、でもまた明日からやろう」と再開すれば大丈夫です。
つまり「サボってしまった=自分はダメ」ではなく、
途切れてもまた続けることが大事なのです。
習慣化と脳の可塑性
習慣化の背景には、
脳の**可塑性(かそせい)**
と呼ばれる仕組みがあります。
可塑性とは、経験や学習によって神経回路が
強化・弱化され、脳の構造が変化することです。
関連する脳の部位
- 大脳基底核:繰り返しの行動が刻まれ、やがて自動化される場所
- 前頭前野:最初の意思決定に使われるが、習慣化が進むと役割が減る
繰り返し行動を「毎日一定の条件」で行うと
、脳の回路が強固になり、やがて意識しなくても
自動的に行動できるようになります。
習慣はリセットされない
一度強化された神経回路は、
行動をやめてもすぐに消えるわけではありません。
ただし使わなければ徐々に弱くなっていくので、
また再開すれば再び強化されていきます。
つまり、途中でサボっても習慣は「完全にゼロに戻る」ことはないのです。
まとめ
- 習慣化には平均66日(個人差18~254日)
- 行動が小さいほど習慣化が早い
- 休んでもリセットはされない、再開すればOK
- 習慣化は脳の可塑性によって神経回路が強化されるプロセス
- 「小さく始めて2ヶ月続ける」ことを意識するのが成功のコツ

筋トレにおける矛盾!?
筋トレで効果を出すには「継続すること」が一番大切です。
そして、そのために有効なのが「習慣化」です。
しかしここで一つ疑問が出てきます。
筋トレを最大効率で行うには
「鍛えた後は2〜3日の休養をとるのが良い」とよく言われますよね。
「あれ?習慣化には毎日やるのが大事じゃなかったの?」
と思った方もいるかもしれません。
実はその通りなのです。
多くの人は“効率的な筋トレ方法”ばかり調べてしまい、
習慣化の仕組みを知らないために途中で挫折してしまうのです。

では、どうすればよいのでしょうか?
答えはシンプルで
「筋肉痛にならない程度の筋トレを毎日続けること」です。
2〜3日の休養が必要になるのは
「筋肉を限界まで追い込んだ場合」です。
一方で、筋肉痛にならないくらいの軽い負荷であれば毎日続けられますし、
これが習慣化のコツでもあります。
最初は“できるだけ小さく始める”ことで
習慣化しやすくなり、筋肉痛もほとんど起こりません。
慣れてきたら、部位ごとにローテーションを組むことで
筋肉を休ませつつ毎日続けられます。
こうすることで筋肉を育てながら、
脳の「ドーパミン報酬系」も刺激され、
行動の神経回路がさらに強化されていくのです。
つまり大事なのは「どんなときも毎日続けること」。
無理のない範囲でコツコツ続けていきましょう。
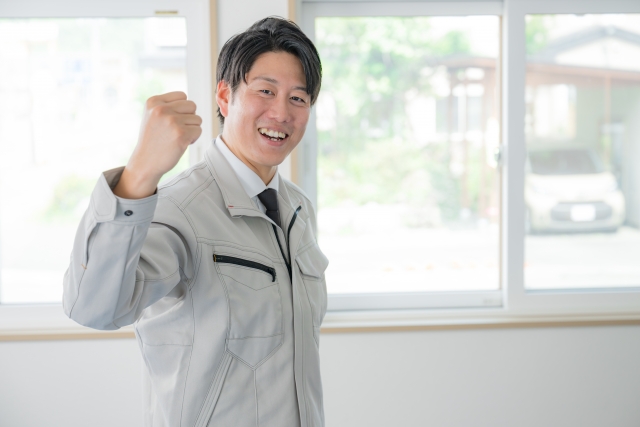
まとめ
今回は習慣化のコツと筋トレを始めていくにあたっての
注意点をご紹介していきました。
今回ご紹介した習慣化のコツを使うことで
前より格段にやりやすくなったかと思いますが、
すべて行動を始めてないと結果が得られません。
何を始めても続かず、
自信をもって人の目を見て
話すことができなかったり、
自信のなさから無理に
自分を大きく見せようとしたり、
何事もネガティブにとらえて
落ち込みやすかったり、
恥ずかしいという理由で
行動をやめてしまったりと、そんな日々より、
自信をもって人の目を見て話せるようになり、
人前でも堂々とふるまえるようになり、
物事をポジティブにとらえて気分も上がり、
行動が続けられるようになり、
スタイルを褒められてさらに自信がつき、
肩こりや腰痛がなくなって
毎日すっきり過ごせるようになる
そんな未来を目指して
まずは一日5回の腕立てから始めてみましょう!

